| □ H29年12月期 A-12 Code:[HE0510] : PLL変調器を用いたFM送信機のブロック図 |
 検索サイトから来た方は… 無線工学の基礎 トップへ 以下をクリックすると、元のページが行き先に飛び、このウインドウは閉じます |
| ■ 無線工学を学ぶ |
|
(1) 無線工学の基礎 |
|
年度別出題一覧 |
| H11年 4月期,8月期,12月期 |
| H12年 4月期,8月期,12月期 |
| H13年 4月期,8月期,12月期 |
| H14年 4月期,8月期,12月期 |
| H15年 4月期,8月期,12月期 |
| H16年 4月期,8月期,12月期 |
| H17年 4月期,8月期,12月期 |
| H18年 4月期,8月期,12月期 |
| H19年 4月期,8月期,12月期 |
| H20年 4月期,8月期,12月期 |
| H21年 4月期,8月期,12月期 |
| H22年 4月期,8月期,12月期 |
| H23年 4月期,8月期,12月期 |
| H24年 4月期,8月期,12月期 |
| H25年 4月期,8月期,12月期 |
| H26年 4月期,8月期,12月期 |
| H27年 4月期,8月期,12月期 |
| H28年 4月期,8月期,12月期 |
| H29年 4月期,8月期,12月期 |
| H30年 4月期,8月期,12月期 |
| R01年 4月期,8月期,12月期 |
| R02年 4月期,9月期,12月期 |
| R03年 4月期,9月期,12月期 |
| R04年 4月期,8月期,12月期 |
| R05年 4月期,8月期,12月期 |
| R06年 4月期,8月期,12月期 |
|
分野別出題一覧 |
| A 電気物理, B 電気回路 |
| C 能動素子, D 電子回路 |
| E 送信機, F 受信機 |
| G 電源, H アンテナ&給電線 |
| I 電波伝搬, J 計測 |
| ■ サイトポリシー |
| ■ サイトマップ[1ama] |
| ■ リンクと資料 |
■ メールは下記まで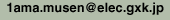 |

|
| 2025年 |
| 03/31 R06/12月期問題頁掲載 |
| 03/31 R06/08月期問題頁掲載 |
| 03/31 R06/04月期問題頁掲載 |
| 03/31 R05/12月期問題頁掲載 |
| 03/31 R05/08月期問題頁掲載 |
| 03/31 R05/04月期問題頁掲載 |
|
|
| |||||||||||||||||||||
 Fig.H2912A12a | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
この問題は、既出問題でFMの直接変調の問題かと思いきや、新しい問題であることが分かりました。PLLを使って周波数変調をかける方式の問題です。どうすればPLLを使って周波数変調がかけられるのか、難しい理論は抜きにして、PLLの復習を簡単にしてから見て行きます。[1]PLLの(簡単な)復習PLLそのものの詳しい原理説明は、H1404A10の問題解説等を参考にしていただくとして、ここでは簡単に復習します。 | |
 Fig.HE0510_a PLLの原理的構成と各部の波形 |
左のFig.HE0510_aは、PLLの原理構成です。「位相同期ループ」の名の通り、ループ回路になっており、フィードバック(負帰還)回路の一種です。 まず、基準となる信号は、水晶発振子や特殊なところでは標準電波のキャリア(搬送波)など、周波数が一定で変動が少ないものを選びます。 基準入力と出力は、PLLのキー部分の一つである「位相比較器」に入ります。「位相」を「比較」するとはどういうことかというと、基準信号と出力の位相のズレに応じた(電圧)出力を得るというものです。 |
位相比較器の出力は「リアルタイム」で、信号の周期ごとに出力されますから、基準入力の周波数と同じ成分を多く含む脈流になっています。これでは、後に繋がる「電圧制御発振器(VCO)」の動作に都合が悪いので、低域フィルタ(LPF)に通し、電圧の変化を平坦にします。[2]FM変調の鍵はVCOPLLを用いた周波数変調では、この電圧制御発振器(Voltage Controlled Oscillator)がカギを握ります。 | |
|
何故かと言えば、「入力電圧に対して直線的に周波数が変化する発振器」は、その入力に音声を加えてやれば、周波数変調出力が得られるからです。 LPFの出力を入力とするVCOは、左の図Fig.HE0510_bのように、入力の電圧に対して直線的に出力周波数が変化する領域を持った発振器です。理想的には、入力電圧が変化しても、出力振幅は変動しません。変化するのは周波数だけです。 この直線範囲に入るように、音声信号にバイアスを掛けてVCOに入力してやれば、VCOの出力には周波数変調波が得られるはずです。 |
 Fig.HE0510_b VCOの入出力特性 |
実際に周波数変調をかける際、周波数偏移量は、この入出力特性の直線部分に十分入る範囲でなければなりませんが、普通は直線範囲の方が十分広くなるように設計可能(この後に述べる構成の、分周器の分周比が非常に大きい場合はこの限りではありません)です。[3]PLLを用いたFM変調器の構成それでは、上で見てきたVCOの動作を利用して、FM(F3E)変調器を構成するにはどうしたらよいかを調べます。 | |
 Fig.HE0510_c PLLを用いたFM変調器 |
左のFig.HE0510_cが構成の一例です。薄黄色で塗った部分がPLLです。上のHE0510_aに比べると、分周器が入っていたり、緩衝増幅器が入っていたりしますが、これらが変調器の本質を決めているわけではありません。 低域フィルタの出力に、変調信号となる音声信号を加算していますが、これが上で書いた「VCOの入力にバイアスを掛けた音声信号を加える」という動作を示しています。 但し、この変調器がまともに動作するには、一つ条件があります。それは、音声入力がない時の、PLLそのものの応答速度が、音声信号の変化に比べて十分遅いことです。 |
|
これはどういうことか…。PLLは負帰還の一種なので、外乱が加えられると、それを元に戻そうとする、ということです。例えば、ある周波数範囲でのずれを1 [ms]で元に戻せる高速応答のPLLがあったとします。これに、10 [Hz](周期100 [ms])の正弦波を加えたら、PLLはこの正弦波による周波数のズレ分に応答して、本来の周波数に補正できてしまいます。信号レベルで言えば、変調波として加えられた10 [Hz]の正弦波を外乱と見なし、それによる周波数偏差を補正しようと、加えられた正弦波と逆位相・同振幅の正弦波がLPFから出力されて、両者加算の結果、VCOの入力はほぼ直流に固定され、得られる信号の周波数はほとんど動かないでしょう。 PLLの応答速度は、通常は高速な方が都合が良いとされますが、この用途では、少なくとも音声周波数よりは十分遅い応答でないと、変調器として不都合になります。PLLの応答速度の設計は、主にLPFの時定数(カットオフ周波数)と分周器の分周比の組合せによって行ないます。 それでは、解答に移ります。 この問題は、まず、PLLを応用した変調器であることに気付く必要があります。それに気付けばAが電圧制御発振器(VCO)だと分かります。次に、Bは、この構成図がPLLの一部をなしていることから、低域フィルタ(LPF)となり、1が正解と分かります。 | |
 |
 |